


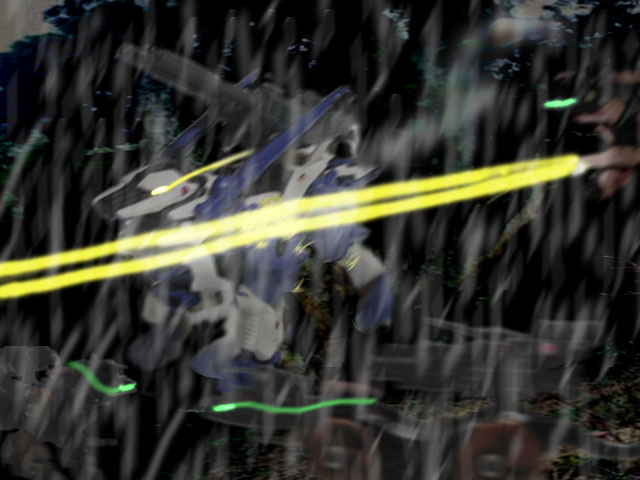

ミューズ森林地帯3 森の中を走り抜ける2体のゾイドがあった。 ヘリック共和国軍所属ハウンドソルジャーとガイロス帝国軍所属ライトニング サイクスである。 時おり突き放そうとハウンドソルジャーが追尾するライトニングサイクスに向 けて背中のビーム砲を放つが、ライトニングサイクスは何事もなかったように それをかわしていく。 「まったくしつこいぜ。新型さんは。」 森で見つかってから2時間、彼は逃げに逃げていた。 さすがのジムの心にもあせりと苛立ちが募ってくる。 (何処か広い場所は・・・・・・・・・。) 彼は自分が戦いやすい場所を探していた。 ミューズ森林地帯はその巨大な森ゆえに穴のあいたように木が生えていない場 所が何箇所かあった。 相手にとっても戦いやすいかもしれないが、自分が戦いにくいまま戦法を組み 立てるよりかはましと判断したのだ。 ひょっとしたら相手は森林地帯での戦闘に慣れているパイロットかもしれない という予感もあったのだ。 「・・・・・・!!よし見えてきた!」 心躍るように言うジム。 目の前に見える、開けた場所に突入するとそこで反転し、サイクスめがけて砲 撃を開始する。 「こんな場所があったのか。ジムはこの森の事をよく知っているようだ。」 そうつぶやくと砲撃をかわすために近くにある木々を盾に身を隠す。 数分後、砲撃がやむ。それを見て広場に踊りでるエドワード。 それを見たジムは、サイクスめがけて突撃をかける。 「おもしろい。」 笑顔を見せるとエドワードもまたハウンドめがけて突撃する。 2機はそのまま激しく衝突する。 「さすが新型、あれぐらいじゃあ何ともないか・・・・!?」 突然、ジムは右腕の違和感に気づく。 「腕がしびれてきやがった・・・・傷口が悪化したのか?」 基地を抜け出す際にアルフレッドに撃たれた傷が悪化し、右腕がしびれで動き にくくなっていた。 「仕方ない・・勝負を急ぐか。」 背中のビーム方で牽制をかけつつ、サイクスに迫るソルジャー。 「勝負に出る気か?まだ早いように思うが・・・!」 そういいながら応戦するエドワード。 「うぉぉぉぉぉ!!」 おたけびにも似た叫びが、ソルジャーのコックピット内にこだまする。 ハウンドソルジャーを一気に接近させ、前足のクローでサイクスを引き裂こう とする。 しかしよけられ逆に懐に入られ、サイクスの牙を胴体受ける。 もがくソルジャー。しかし一向に抜け出せない。 時間がたつにつれ、ハウンドソルジャーの動きが段々鈍くなる。 「くそっ、このままやられるか!」 そう言うと強引にサイクスの前足に噛みつこうとする。 しかしそれも失敗に終わりさらに頭を踏みつけられると言う結果に終わる。 「これで終わりだジム!」 その言葉に呼応するように同時にハウンドソルジャーの背中に装備されている ジェットエンジンに火がつく。 「なんだ!?」 ハウンドソルジャーはそのままの体制で、地面の上をすべるように進み始める。 その動きに思わず胴体から牙を抜くサイクス。 牙が離れると滑りながら機体を起こし、体制を整える。 「すさまじい根性だな。感心させられる。」 体制を整えたソルジャーに向かって間をおかず、攻撃を仕掛けるサイクス。 必死に応戦するソルジャー。 距離が近づくにつれ、全兵器を使用して必死に近づけまいとする。 「よくがんばった。が、ここまでだ!!」 「このままではおわらさねぇよ!!」 一発のミサイルがサイクスの前で光り輝く。 「信号弾だと!?めくらましか!!」 エドワードが気づいたときには、ハウンドソルジャーの機影は何処にも見えな かった。 夜の暗闇と豪雨による雨の音で、まったく相手の場所がわからなくなっていた。 「何処へ行った!?」 それに答えるかのように雨の音を押しのけて、あたり一帯の木々が大きな音を 立ててざわめく。 「!!なんだと!?」 上空に暗視カメラをあてて見たエドワードは驚愕した。 あたりの木々をムササビのように飛び移るハウンドソルジャーの姿があったからだ。 「これでどうだ!!」 木の瞬発力を使い驚異的なスピードでサイクスめがけて突っ込んでくる。 ハウンドソルジャーの前部には二本の槍が突き出ていた。 クロスソーダである。 一瞬の隙をつかれてよける暇などエドワードにはなかった。 しかし彼は必死の思いでサイクスを動かす。 そして。 クロスソーダはサイクスの背にあるビーム砲の砲身一本とコックピットハッチ を剥ぎ取っていた。 「こなくそ!!」 もうろうとした意識の中でビーム砲のスイッチを押すエドワード。 ズギャン エドワードが放った一撃は、ハウンドソルジャーの尾に装備されたスタビライ ザーに命中する。 その爆発でハウンドソルジャーは、着地に失敗して転げ落ちる。 「がぁ・・・!」 衝撃に思わず悲鳴を上げるジム。 2機のゾイドは負傷し、その場で動かなくなる。 あたりは雨の降り注ぐ音だけがあたりを支配していた。 同時刻、アルフレッド達は同じ森林の中をかけていた。 本来ならば、森の北から攻める部隊として参加予定であったが、エドワード機 失踪の為、アルフレッドが中心となって捜索隊としてこの森に入ったのだった。 「さっき、この奥の場所で無数の光が観測された。戦闘である事は間違いない。」 森林地帯の地図とナビゲーションシステムを使って、光の元を探す。 アルフレッドのほかにはセイロンと第1戦隊が随伴している。 ヒィルの機体は損傷が激しかった為、修理する為に帝国領内へ戻ったので、 今回の作戦は不参加である。 「・・・・・うん・・・へっ、生きてたか。俺もよっぽど悪運が強いらしいや。・・・」 気がついたジムは、モニター画面をサイクスの方へと向ける。 「これで動き出したら敢闘賞もんだな・・・。ま、それはこっちも同じか。」 コンソールをたたき、機体ダメージを画面に表示させる。 機体の何処を見ても損傷していない個所はなく、システムがフリーズせずに動 いている事自体不思議であった。 「さて相手のパイロットの顔でも見とくか。生きてたら助けてやんねえと。」 そう言うと機体から降りサイクスの方へと向かう。 降りしきる雨が、体を突き刺すように降り注ぐ。 「なっ!?」 何とかサイクスのコックピットまで這い上がったジムは驚愕する。 そこには誰もいなかったのだ。 「おいおい、俺は無人機とやりやったってのか・・・・。」 「心配するな。ちゃんとした人間だったさ。」 その声とともにジムの背中に銃が押し付けられる。 「その声・・・・おっさんかい。道理でしつこいわけだぜ・・・・。」 「おまえさんが敵とわかった時、どのくらいの腕か試したくなってな。」 うれしそうな表情で言うエドワード。 「で、俺の試験結果は?」 「もちろん合格だ。ジム、おまえさんほどの腕はそうざらにはいないさ。 わしが保証してやるよ。」 「へっそうかい。で、その拳銃いつまでつきつける気だい。いいかげん手が疲 れたぜ。なんせ右腕は麻痺気味なんでな。」 「麻痺?戦闘中からか。本当におまえは無茶をする。手当てしてやる。ちょっと そこのシートに座れ。」 そう言うと銃を下ろし、コックピットの後部から救急箱を出す。 ジムもエドワードの言葉に従いコックピットシートに座る。 「いいのかい。俺は敵だぜ。」 「戦闘が終われば敵も味方もない。お互いを助け合わないとな。お前もその気だ ったんだろ?」 そういいながら右腕の手当てを施すエドワード。 「せっかくののみ友達だ無駄に死なせはせん。はっはっは・・・・・。」 『こちらアルフレッド。エドワード大佐無事なら応答を・・・!!』 「・・!アルめ作戦に参加せず何故ここに・・・・・。」 「・・・・作戦?」 「おっと、おまえさんはそこまでは知らなかったのか。今晩この嵐を利用してロ ブ基地を中心にたたく作戦だ。」 「今晩!?もう作戦は始まっているのか!?」 驚きを隠せないジム。 「時間的にはもう総攻撃は・・・・始まってるな。」 時計を見ながら言うエドワード。 「・・・・くっ。」 悔しそうな顔をするジム。 「・・・・・・おまえの相棒はまだ動くよう出し、さっさと行けばいい。」 「!?・・・いいのか?」 「おまえはわしの友人だぞ。敵であろうが関係ないさ。さっさと言ってこいや。」 そう言うと肩をたたく。 「頑張れよ。次に戦場であったときは負けんからな。」 「・・・ああ。またなおっさん。」 そう言うとコックピットから降り、ハウンドソルジャーへ向かって走り出す。 『・・・・・応答願います。』 「おっと返答を送るのを忘れてとった。アルもあいつぐらい前向きにだったらわ しを超えられるのにな。」 笑いながらアルフレッドの通信を横目につぶやいた。 「・・・・・ああいう軍人もいるんだな、帝国にも。」 そうつぶやきながら機体を東へと向ける。 しばらくしてアルフレッドがエドワードのもとに姿を現す。 「ようやく来たか。」 目の前に迫る黒いセイバーを見てつぶやくエドワード。 アルフレッドは機体をかがませるとコックピットから降り、エドワードのもと へ走る。 「大佐ご無事で。敵は?」 「あいつか、あいつならさっきこの場を離れたよ。」 「それでは今から追撃に・・・。」 サイクスの下で雨宿りをしながら二人は話す。 「そんなことをしなくとも別にかまわんさ。もう作戦は動いているんだろう?」 手持ちの携帯食料をかじりながら言うエドワード。 「はい。しかし私は指令より大佐を探すように言われました。」 「わしというよりこいつのほうが心配だったんだろうさ。」 そう言うとサイクスのほうへと目をやる。 「なぁアル、出撃前にお前にいろいろいったが・・・・忘れろ。」 「??・・・どういうことですかそれは。」 不思議な顔をするアルフレッド。 「気にすることはない。ただ強制するような事をいって悪かった。、れだけだ。 お前はお前の好きな道を行け。それが帝国を裏切るような事になっても。 人が信念を持って生きるという事は並大抵な事ではないが、お前にはできる かもしれんしな。後、こいつもこんな風になっては、お前に譲れんしな。」 苦笑しながら言うエドワード。 「・・・大佐。」 「さぁそろそろ基地に帰ろうか。」 「了解しました。」 二人はセイバーに乗るとセイバーの照準をサイクスに合せる。 「すまんが野ざらしというわけにはいかんのだ・・・・。やれ。」 悲しい目をしたエドワードがそういうと、アルフレッドは握り締めた操縦桿に ある発射ボタンを押す。 一斉射をうけたサイクスは、大きな爆音を響かせて一瞬あたりを明るくすると 粉々に砕け散る。 それを確認するとセイバーはその場を去る。 サイクスのあった場所は火の海となっていたが、この大雨で30分とかからず 火は消えていた。 あれから小1時間ほど走った頃だった。何かの異変に気づくジム。 「・・・・敵か?」 すさまじいまでに研ぎ澄まされた感が、辺りにいると思われる敵に反応する。 少し経って、敵機接近の警報がなる。 「やっぱりそうかい!!」 しかしジムの反応より先に敵からの砲撃か来る。 それをまともに受けてその場に沈黙するハウンドソルジャー。 「くそ、さっきの戦いであっちこっちやられていて、機体の反応が鈍ってやが る。」 動きのないハウンドソルジャーを見て少しずつ詰め寄ってくる敵機。 「改造ヘルキャットかい・・・。」 近づく敵機の機影を見てつぶやくジム。 彼の前に現われたのは、3機の改造ヘルキャット、ハイ・キャットだった。 「・・・・よしこれでなんとか。」 そう言うと操縦桿を握り機体を起き上がらせる。 「こいつは少々のがたが来たぐらいじゃあ負けやしないんだよ!!」 起き上がるハウンドソルジャーを見て再度攻撃を開始するハイ・キャット。 何発か喰らいながらも攻撃をかわすジム。 必死の反撃に出るジム。攻撃をうまくよけ、1機のハイ・キャットの懐に飛び込むとコックピットを噛み砕く。 「ひとつ!次は!?」 ジムがほかに目をやったとき、すでにハイ・キャットは目の前に来ていた。 見つけるとともに大きな衝撃を受ける。 衝撃の大きさにコンソールに頭を打ちつけるジム。 「こ、ここまでか・・・・。」 薄れゆく意識の中で覚悟を決める。 ハイ・キャットの前足が、コックピットめがけて振り下ろされる。 しかし一向に衝撃がこない。何があったのか確かめようとするジム。 ハイ・キャットは噴煙を上げてその場に倒れこんでいた。 「な、何が・・・・。」 しばらくモニターを見ていると、青い機体がハイ・キャットと戦闘を繰り広げ ていた。 「・・・・・シールドライガーか?」 しかし、シールドにしてはスピードや運動性能が断然違う。 「ありゃ一体・・・・。」 そこでジムの思考が途絶えた。 「・・・・・ん、ここは?」 次に気がついたときには、見慣れないコックピットだった。 しかし、キャノピー越しに外が見える。 「よかった・・・・もうおきないかと思った。」 聞きなれた声だった。それはジムにとって懐かしく安心を与えた。 「し・・・シンシア、なんでお前が?」 目の前にいたのは、彼の幼馴染のシンシアだった。 「何でって、あんたが最後に通信した後、定時連絡がないから心配できたんじ ゃない。」 「・・・・・・心配だからって・・・・よく許可が下りたな。」 「基地指令自らの命令だったから許可なんていらなかったわよ。」 「・・・・・へ、あのおっさんもなかなか。」 笑みを浮かべるジム。 「しかしこの機体は・・・。」 副座のついたこの機体に興味津々のジム。 「これはブレードライガー、新型機よ。」 「これがブレードか・・・。ほかにパイロットがいないって事はお前が操縦 を・・・?」 「当たり前よ、ただの研究員だと思わないでよね。これで私に借りができたわね。」 優位に立った笑みを浮かべるシンシア。 「ち・・・・そういえばあいつはどうなったんだ?」 気が落ち着きハウンドソルジャーのことが気になるジム。 「・・・・あの子はもうだめよ。最後に受けた攻撃でコアに傷が・・・・。」 悲しい表情をするシンシア。 「・・・・・そうか。俺に腕がないばっかりに・・・・・。」 ぶつけようのない怒りが込み上げてくる。 「コアはちゃんと葬っておいたから安心して。」 「・・・・いろいろとすまないな。今回の事といいお前には迷惑ばっかりかけ ている、情けないよ。」 「気にしなくても、わたしも好きでついてきてるんだから。」 そう言うと笑顔を見せる。 「そうだったな。だから俺も安心して戦えるんだ。」 その言葉を聞いて赤くなるシンシア。 「なーに照れてんだよ。」 「う、うるさわね!!けが人なんだから静かに寝てなさいよ!」 二人のいつものケンカが、ミューズの森に響き渡るのだった。 数日後、ジムとシンシアの姿はロブ基地の港にあった。 「まさか二人して中央に戻る事になるなんてな。」 「どうやっても離れられないみたいね、私たち。」 ジムは怪我のために中央に戻る事となり、シンシアはハウンドソルジャーを失 ったため、中央の研究所に戻る事となったのだ。 「ま、腐れ縁はどうやっても切れねえもんだぜ。」 「一生、離れられないみたいね。」 「そうだなこのままじじ、ばばになるまで一緒にいるか。」 「な、何それ!プロポーズのつもり!?」 ジムの言葉に赤くなるシンシア。 「さーてそろそろ乗船しないとなぁ。」 そう言うとさっさと船に乗り込む。 「あ、まちなさいよ!ちゃんと答えなさいよ!」 そう言うとタラップを駆け上がるシンアシア。 二人の旅立ちは今始まったばかりである。 後書き10 バトストMENUに戻る 前の話へ行く 次の話へ行く